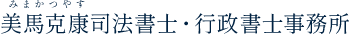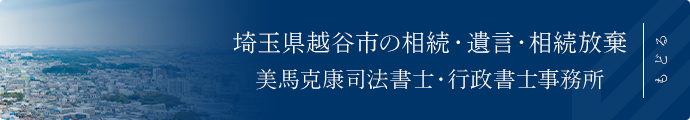越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
営業時間 8:30~18:30
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺言書について、遺言書作成案内、遺言、遺言能力、共同遺言の禁止、遺言書の必要性、死亡危急者遺言、遺言効力の発生時期に分けて解説しています。
亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
ご家族を守るための 遺言書作成

遺言とは、亡くなった人が自分の財産を誰にどのように引き継がせたいかの意思を示す手段です。遺言書は、その意思を書き記した書面です。遺言者の死後、遺言の内容にそって財産を相続人間で分割し、遺言が執行されます。
不幸は突然に訪れます。残されたご家族間の紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の作成お任せください。
当事務所の遺言書作成
公正証書による遺言書作成は、当事務所に一度お越しいただきます。
公証役場にも一度行っていただきます。美馬も証人として出頭いたします。
※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。

- 1
- 15
- 17
- 18
- 19
- 21
遺言とは
遺言とは
- 遺言とは、人の生前における最終の意思表示です。
遺言制度は、その意思表示に法律的効果を認めて、死後にその実現をはかるものです。
- 被相続人の最終の意思表示は、これを尊重するのは当然といえますが、遺言が効力を生ずるときは、被相続人は死亡しており、遺言の意味内容や効力の有無について争いが生じるおそれがあります。
- そこで、民法は遺言に厳格な方式を定めたうえで、その方式にしたがった遺言がされる限り、遺言の内容の実現をはかることとしています。
遺言の性質
遺言の性質
- 遺言は、様式行為であり、民法の定める方式にしたがわなければなりません。民法は、遺言書の作成について一定の方式を要求しています。これは、遺言の存在を確保して、遺言者の真意を明確にし、あわせて遺言書の偽造、変造の防止をはかることとしているのです。
- 遺言は、遺言者の一方的な意思表示により行われ、かつ、相手方のない単独行為の性質を有します。すなわち、遺言は、遺贈など遺言によって利益を受ける者があっても、その者が相手方となるわけではなく、自らの意思のみにもとづいてすることができます。
- 遺言は、遺言者の最終的な意思表示ですから、その意思を確保するためには、遺言者の独立の意思にもとづいておこなわれる独立行為でなければなりません。そのため、遺言については、遺言者以外の者の同意を要せず、また第三者が代理してすることはできません。
- 遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じますので、死因処分といわれるものに属します。死因処分としては、遺言のほかに死因贈与がありますが、遺言は単独行為であって当事者の契約である死因贈与とは異なります。
遺言事項の原型
遺言事項の原型
- 遺言事項、すなわち遺言をすれば法的に効力が生じる事項は、民法その他の法律で定められた事項(解釈上認められるものを含む)に限られます。
- 民法上遺言事項には、次のような事項があります。
① 身分に関する事項として、認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定があります。
② 相続に関する事項として、推定相続人の廃除または廃除の取消し、相続分の指定、または指定の委託、遺産分割方法の指定、または指定の委託、遺産分割の禁止などがあります。
③ 相続以外の財産処分に関する事項として、遺贈、遺贈の効力に関する定め、配偶者居住権の遺贈などがあります。
④ 遺言の執行に関する事項として、遺言執行者の指定または指定の委託、遺言執行者に関する定めがあります。
⑤ 解釈上、遺言でもすることができるとされている事項として、特別受益の持ち出しの免除、祭祀主宰者の指定などがあります。
遺言能力
遺言能力
- 遺言は、人の最終意思を尊重する制度ですから、民法は、一般の行為能力のない者も遺言ができるよう未成年者、成年被後見人、被保佐人、および被補助人の行為能力の制限に関する民法総則の各規定は、遺言には適用しないと定めています。
- しかし、遺言も法律行為のひとつですから、遺言時において、遺言者が遺言能力(遺言の意味内容を理解することができる意思能力)を、有していなければなりません。
- 未成年者でも滿15歳に達した者は、意思能力を有する限り、親権者などの法定代理人の同意なしに、単独で遺言をすることができます。
- 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに限り、成年後見人の同意を必要とせずに、医師二人以上の立会いにより遺言をすることができます。
- この場合に、立ち会った医師は、遺言者が遺言時に精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態でなかった旨を、遺言書に付記して署名押印し、秘密証書遺言では、封紙にその旨を記載して署名・押印しなければなりません。
- 被保佐人や被補助人については、特に制限はなく、遺言能力があれば、保佐人や補助人の同意を要せずに遺言をすることができます。
総説
総説
- 遺言能力を欠く者がした遺言書は無効です。遺言能力は、遺言のときに有していれば足り、その後、遺言能力を喪失しても遺言の効力に影響はありません。
- 遺言能力の有無は、その性質上、個々の事案ごとに判断せざるをえません。裁判例は、基本的には遺言能力を受理弁識能力とし、遺言時において、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力を有していなければならないとしています。
遺言能力を認めた事例
遺言能力を認めた事例
- 84歳の高齢者がした公正証書遺言につき、財産は全部長男にやる旨の口授をした当時の遺言者には、軽度の多発性脳梗塞がみられるものの、脳血管性痴呆と診断することはできないとする医師の鑑定を採用し、遺言者には遺言の趣旨を口授し、公証人の筆記の正確なことを承認する能力があったものと認めた事例があります(東京高等裁判所判例 平成10年2月)。
- 加齢にともなう知的老化の兆候が認められる94歳の高齢者がした公正証書遺言につき、遺言書作成の際の医師の判断、公証人とのやり取りのほか、遺言の内容が打合わせ済みであったこと等、その後の治療経過などから遺言能力が、あったものと認められます。そして、遺言者が事前に了承していた遺言の内容を、公証人から各条読み聞かせられたのに対し、その都度自ら口頭で「その通り相続させる」と返答して作成したもので、当該遺言に方式上の瑕疵はありません(東京高等裁判所判例 平成10年8月)。
遺言能力を認めなかった事例
遺言能力を認めなかった事例
- 妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言者が、その後妻の生存中にした妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、遺言者がうつ病・認知症であり、遺言当日に不穏な行動がなかったとしても、うつ病・認知症や投薬の影響で判断能力が減弱した状態にあり、遺言事項を具体的に決定し、法律効果を弁識するのに必要な判断能力を備えていたとは言えないとした事例があります(東京高等裁判所判例 平成25年3月)。
- また、92歳の高齢者がした公正証書遺言につき、遺言書作成の半年前には、遺言者の記憶障害などの精神障害の程度は顕著であり、遺言者自身が財産の管理、処分ができる状態ではなく、公正証書遺言の内容や、遺言者の心理検査や医師による診察の結果などを、踏まえると、遺言者が遺言の内容(相続財産の内容や分配方法など)を理解する能力を有していたとは言えないとされた事例があります(大阪高等裁判所判例 平成30年6月)。
共同遺言の禁止
共同遺言の禁止
- 遺言は、各自が単独で、その自由な立場ですべきものですから、二人以上の者が同一の証書で共同遺言をすることは禁止されています。
共同遺言の禁止は、いずれの方式による遺言にも適用されますが、実際上、自筆証書遺言の場合に、問題になります。
- たとえば、夫婦が互いのことを考え、自筆証書遺言をしようと同一の証書に連名で遺言をすると無効になります。もっとも、夫婦が別々の遺言書を、同一の封筒に入れてあるような場合では、共同遺言とは言えません。
- 判例は、契印された4枚綴りの紙に3枚目までが、夫甲が自己所有の特定不動産をこの家の二名に遺贈する旨の甲の遺言書の形式をなし、4枚目は、妻乙が、自己所有の特定不動産を、この家の1名に遺贈する旨を遺言書の形式をなしていた自筆証書遺言につき、次のように判断しました。すなわち、各人の遺言書をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、共同遺言にあたらないとしています(最高裁判所判例 平成5年10月)。
- 共同作成名義の遺言について、その一方に方式違背がある場合、判例は、甲が妻乙との連名で、甲が子供らにどの不動産を与えるかを記載し、最後の項目にその財産は両親がともに死亡したのちに行い、父が死亡したときは、まず母が全財産を相続する旨の自筆証書遺言をした事案があります。
- この事案について、遺言者は、全文を甲が自署し乙の署名も代書したもので、乙について氏名を自署しない方式の違背があるが、なお共同遺言にあたるとして、その全体を無効としています(最高裁判所判例 昭和56年9月)。
- 夫の不動産を、子に与える旨の夫婦共同作成名義の自筆遺言証書につき、一見共同遺言のような形式となっていますが、夫が妻の知らない間に単独で作成し、妻も同じ意思であることを示す趣旨から、自己の氏名の下に妻の名を書き加えたものであって、夫の単独遺言として有効としたものがあります(東京高等裁判所決定 昭和57年8月)。
遺言の方式の種類
遺言の方式の種類
遺言には、普通方式による遺言と特別方式による遺言があります。
前者が本来の方式であって、その種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言および秘密証書遺言があります。後者は、例外的な場合に認められ、危急時遺言と隔絶地域遺言があります。
普通方式の遺言の比較
普通方式の遺言の比較
- 普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種の遺言を比較すると、次のような特色が認められます。
- 自筆証書遺言
① 方式
遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印します。ただし、遺言書に添付した財産目録については自書を要しません。
② 長所・短所
・遺言者本人のみで簡単に作成ができ、秘密にできます。
・遺言者が自ら保管します。そのため、紛失、偽造・変造、隠匿のおそれがあります。
・方式違背、文章の意味不明でその効力が問題となるおそれがあります。
・家庭裁判所の検認が必要です。
・遺言者の申請により、法務局で保管することができ、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しません。
- 公正証書遺言
① 方式
証人2人以上が立会います。
遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
遺言者・証人が承認して、署名・押印し、公証人が署名・押印します。
② 長所・短所
・遺言の内容が明確であり、紛争の生ずるおそれは少ないです。
・原本を公証人が保管するため、紛失・偽造などのおそれがありません。
・証人や費用を要し、公証人・証人には、遺言を秘密にできません。
・家庭裁判所の検認は必要ありません。
- 秘密証書遺言
① 方式
遺言者が遺言書を作成して、署名・押印のうえ封印します。
その封書を、公証人・証人2人以上の前に提出します。
そして、自己の遺言書の旨および氏名・住所を述べます。
公証人が日付および遺言者の口述を封書に記載し、遺言者・証人とともに署名・押印します。
② 長所・短所
・証人および公証人の関与が必要です。
遺言の内容は秘密にできますが、作成自体は秘密にできません。
・方式違背、文意不明で効力が問題となるおそれがあります。
・遺言者は自ら保管します。偽造・変造は防止できます。
・家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言のすすめ
遺言のすすめ
- 自分の有する財産を誰に承継させるかについて、遺言という形で自己の最終的な意思を明示して、関係者に正しく伝えることは、自己の意思を確実に実現するとともに、残された家族の間で遺産をめぐって争いが生ずるのを未然に防止するうえでも大切なことです。
- 先に紹介した普通方式の遺言のなかでは、公正証書遺言によるのがもっとも安心・確実な方式と考えられます。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要であり、手数料がかかるという点はあります。しかし、法務大臣から任命された公証人が、遺言者の口述を筆記して作成するもので、その内容は法律的に明確であって、原本は公証役場に保管されるため、その紛失や偽造などのおそれがありません。
- 自筆証書遺言は、作成した遺言書を自ら保管しておくため、その紛失や偽造・変造のおそれがあります。しかし、令和2年7月から施行された、法務局における遺言書保管制度を利用すると、これらを防止することができるようになりました。
遺言書における相続人などの表示
遺言書における相続人などの表示
- 相続人・受遺者の表示
相続させる相続人の表示は、氏名・遺言者との続柄・生年月日をもって特定します。
相続人以外の親族や知人等に遺贈する場合には、氏名・生年月日・住所を記載して、これを特定するのが一般的です。
- 不動産の表示
不動産の表示については、これを特定できる程度に記載すれば、遺言としての効力に欠けるところはありません。
土地の場合には「◯◯町◯◯番の土地」や「◯◯町◯◯番地 家屋番号◯◯番の建物」と記載することでも充分です。
遺言者の有する財産の全部または不動産の全部を、相続人一人に相続させるのであれば、「財産の全部」または「不動産の全部」と記載する事でも通用します。
- 預貯金の表示
預貯金の表示については、「◯◯銀行◯◯支店、口座の種類、口座番号」により特定するのが一般的です。
総説
総説
- 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文、日付および氏名を自書(手書き)し、押印して作成するものです。加除などの変更も定められた方式に従う必要があります。
- 遺言書の保管は、遺言者本人が行います。遺言書は、遺言者死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。なお、自筆の遺言書に財産目録を添付する場合には、同目録について自筆要件が緩和されました。
- 令和2年7月10日から、法務局において自筆の遺言書を保管できるサービスがスタートしました。
自書の意義
- 自筆証書遺言が有効に成立するためには、遺言書の作成時に自書能力(文字を知り、かつ自らの意思で筆記する能力)を有していなければなりません。
- 自書とは、文字通り遺言者が自らの手によって筆記すること(手書き)をいいます。民法が自書を要件としたのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからです。
- 他人に下書きをしてもらい、遺言者がそれを書き写した場合はどうでしょうか。遺言者が文字を解することができなければ無効と解すべきですが、文字が書けて理解しうるものの、的確な表現力に欠けるという程度であれば自書とみてよいでしょう。
- 本人の自筆か否かの点に、筆跡鑑定の結果が用いられることがありますが、その結果のみが決め手になるわけではなく、事案を総合的に検討して判断すべきと考えられています。
添え手による自筆証書の作成
添え手による自筆証書の作成
- 他人の添え手による補助を受けて遺言書を作成した場合、その遺言書は有効か否か、問題になるところです。
- 判例は、運筆について他人の添え手による補助を受けて作成された自筆証書遺言は、原則として無効であるとしつつ、遺言者が証書作成時に自書能力を有しており、かつ添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけで、他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる場合には、有効な自書があったものと解すべきであるとしています。
- ただし、遺言者の妻が、白内障による視力の減退と脳動脈硬化症の後遺症による手の震えのため、単独で文字を書けない遺言者の手をとって遺言者の声にしたがって積極的に手を誘導しつつ作成したものは、自書の要件を欠き無効であるとした判例があります。
- 次に裁判例を紹介します。
① 他人がした添え手は、単に始筆、改行、字間の配りや行間を整えるため、遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、または遺言者の手の動きが望みに任され、単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、筆跡上添え手者の意思が介入した形跡のないことが判定できるから、自書とは認められないとしました。
② 他人の添え手による補助を受けて作成した自筆証書遺言が、筆跡から遺言者の真意にもとづくことは明らかとはならないなどの事実関係のもとでは、自書の要件を欠き無効としたものがあります。
③ 遺言者は自書能力を有し、単に筆記を容易にするため添え手による支えを借りて、自書したもので、運筆に添え手者の意思が介入した形跡はないから、自書の要件を満たし有効としたものがあります。
- 判例は、遺言の様式性の緩和に努めてきたといわれていますが、「自書」については、自筆証書遺言の本質的な要件であり、厳格に解すべきとしています。自書が困難な場合には、公正証書遺言を利用するのがよいでしょう。公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すれば足り、その筆記は公証人が行います。
パソコン、ワープロなどによる作成
パソコン、ワープロなどによる作成
- 自書は、外国語や略字、速記文字でも差し支えありませんが、パソコンやワープロ、タイプライター、点字器などの機器を用いて作成したものは、自書とは言えず遺言としての効力を生じません。
- 筆記具や用紙、その他の素材については、特段の制限はなく、便箋、レポート用紙、ノート、チラシの裏などを使用しても差し支えありません。
- カーボン複写の方法で作成した遺言書については、手本をなぞると筆跡を複写できるなどの問題があります。しかし判例は、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないとしています。
- この点について、カーボン複写で作成された遺言書の筆跡と鑑定資料中の原告(受遺者)の筆跡との共通性が認められ、また同じ誤字や旧字体の使用があること、その他の事情を考慮して当該遺言書は、原告の偽造であるものであるとした事例があります。
- 自筆証書をコピーして作成した遺言書は自書の要件を満たしません。また、ビデオや録音テープによる遺言も認められません。
日付の記載
日付の記載
- 遺言書には日付を記載しなければなりません。日付の記載は、作成時の遺言能力の有無や、内容の抵触する複数の遺言の先後を確定するために要求されるものです。自書のない遺言書は無効です。ゴム印などによる記入は、日付の記載がないと判断されます。すなわち無効です。
- 日付は、暦上の特定の日、すなわち○年○月○日を明かにして記載しなければなりません。「第○回目の誕生日」とか「古希祝賀の日」というような記載でも作成日付が客観的に特定できると解されています。
- 裁判例には、「平成元年11月末」の記載につき、「平成元年11月30日」を表示したものと解して有効としたものがあります。これに対し、「昭和41年7月吉日」と記載された遺言書(いわゆる吉日遺言)は、暦上の特定の日を表示するものとはいえないとしています。
- 「年月」の記載はあるが、「日」の記載のない遺言書はどうでしょう。
判例は、年月のみで日の記載のない遺言は無効であるとしています。
- 登記先例も遺言書の日付が「昭和26年5月」とあり、日の記載がないときは、家庭裁判所の検認をえたものであっても、当該遺言にもとづく登記の申請は、受理すべきではないとしています。また、「年」の記載がなく「月」のみの記載では、その要件を満たしません。
記載されるべき日付
- 日付は遺言書を作成した日(遺言書全部を完成させた日)を記載します。判例は、「昭和48年8月27日」に作成した遺言書の日付を「昭和28年8月27年」と誤記した事案につき、誤記であることおよび真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りは遺言を無効にするものではない、としています。
- もっとも故意による不実記載、たとえば遺言書作成日より2年近くさかのぼった日を記載した遺言書は、日付のない遺言書と同視すべきものとして無効とされています。
- このように、遺言書に記載されるべき日付は、遺言が成立した日、すなわち遺言の方式要件がすべて充足された日の日付であり、判例は、遺言書のうち日付以外の部分を署名押印し、その数日後に当日の日付を記載して、遺言書を完成させた場合には、特段の事情がない限り、その日付を記載した日に作成された遺言書として有効であるとしています。
- また、遺言者が、入院中の日に遺言書の全文、同日の日付および氏名を自書し、退院して9日後(全文等の自書日から27日後)に押印した事案につき、押印日の日付が記載されるべきとしつつ、遺言が成立した日と相違する日付が記載されているからといって、ただちに当該遺言が無効となるものではないとしたものがあります。
日付の記載場所
日付の記載場所
- 遺言書に日付を記載する場合、その本文ののち、署名の前にするのが普通ですが、その他の場所でも差し支えなく、遺言書を入れた封筒が封印等され、その封筒に日付が自書されていれば封筒もその遺言の一部と解して、有効とするのが一般的です。ただし、開封状態で遺言書が封入され、その封筒に日付が記載されていた場合には、遺言書と封筒の一体性が認められず、日付の記載がないものと判断されるでしょう。
- 遺言書が数葉にわたる場合でも、日付の記載は一葉にされていれば足ります。
氏名の自書(署名)
氏名の自書(署名)
- 遺言書には、遺言者自身が氏名を自書(署名)しなければなりません。氏名の自書は、遺言者本人を明確にし、かつ、遺言が真意に出たものであることを明確にするためのものですので、氏名を自書していない遺言書は無効です。遺言書は数葉にわたる場合でも署名は一葉にしていれば足ります。
- 氏名は、戸籍上の氏名を書くのが一般的ですが、普段、「國」を「国」、「實」を「実」などと記載している場合は、普段使用している文字で差し支えありません。
- また、単に氏または名だけでも、あるいは通称名やペンネームなどを用いても遺言者が誰であるかを特定できれば、差し支えありません。
- 登記実例も次のように解しています。
① 遺言者の名だけが自署された遺言書でも、本人を明示している場合には差し支えありません。
② 「母花子より ㊞(氏の印)」と、自署された遺言書につき、受理して差し支えないとしています。
押印
- 遺言書には、氏名の自書に続けて押印をしなければなりません。遺言者の押印を書く遺言書は、その中に遺言者の押印と同視しうるものがあるなどの特段の事情がない限り、無効というべきです。
- 押印を要件としたのは、全文の自書とあいまって遺言者の同一性および真意を確保するとともに、重要な文書には作成者が署名しその名下に押印するという、我が国の法慣行ないし法意識に照らして、文書の完成を担保することにあります。
- 判例には、日本に40年居住し遺言書作成の約2年前に帰化したが、日本語はカタコトを話すに過ぎない元ロシア人が英文で作成し、署名のみをした自筆証書遺言につき、有効としたものがあります。
- 使用する印は実印に限らず、認印でも足ります。指印について、判例は、指印をもって足りると解しても遺言者の真意の確保に欠けるところはなく、我が国の慣行ないし法意識にも反しないとして、積極に解しています。他方、いわゆる花押について、判例は、印章による押印と同視することはできないとして、消極に解しています。
- なお押印は、遺言者本人がするのが原則ですが、他人がその依頼を受けて面前で押印するのは、差し支えありません。
押印の場所
押印の場所
- 押印の場所については、署名をし、その名下(名横)に押印するのが通例ですが、署名の下(横)ではなく、封筒の封じ目に押印したものでも、遺言書と封筒の一体性が認められる限り、押印の要件に欠けるところはありません。
- 裁判例として、遺言者の氏名のみで押印を欠くものの、二枚からなる書面の1枚目と2枚目にまたがって契印がある場合、自筆証書遺言として有効としたものがあります。
- 他方、遺言内容の記載された書面には署名押印を欠き、検認時には、すでに開封されていた封筒に署名押印がある場合、当該書面と封筒が一体として作成されたと認めることはできず、遺言者の署名押印を欠くとして無効としたものがあります。
契印その他
契印その他
- 遺言書が数葉にわたる場合、判例は、全体としてその数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認できれば、そのうちの一葉に、日付、署名、捺印が適法にされている限り、契印や編綴がなくてもよいとしています。
- 財産目録を添付する場合も、遺言書本文部分の間に契印がなくても差し支えありません。
- また、遺言書は、封筒に入れられ封印されることも多いようですが、封入や封印は自筆証書遺言の要件ではありませんので、それがなくても差し支えありません。
加除・訂正その他の変更の方法
加除・訂正その他の変更の方法
- 遺言書中の文字に加除その他の変更をする場合には、次のようにします。
① 遺言者が変更の場所を指示し、
② これを変更した旨を付記して特にこれに署名し
③ 変更の場所に押印しなければ、その効力を生じません。
- 具体的には、訂正箇所を線で抹消して字句を加入して押印したうえ、その行の欄外に「○字加入」と付記して署名するか、遺言書の末尾に「第○条中「○○」を「○○」と訂正」と付記して署名します。
- 判例は、数箇所文字を書き改め押印しているが、変更の付記も署名もない事案につき、明かな誤記の訂正である場合には、その方式の違背は効力に影響を及ぼさないとしています。
- 加除・訂正が方式を具備していない場合の効果について、裁判例は、遺言書全体が当然に無効になるのではなく、加除・変更がなかったものとして有効であり、その記載自体から遺言者の真意を確認するについて、まったく支障がないときは、遺言の効力に影響をおよぼぼすものではないと解しています。
- また裁判例は、方式違背の変更自体は無効であり、結果として変更が加えられる前の部分が判読可能であれば、その内容で遺言が有効となりますが、判読不可能など部分的に毀滅されたのと同じ影響があったと認められる場合には、当該部分に限って効力が失われるとしています。
- 訂正行為をするという遺言者の真意を考慮すると、むしろ訂正後の部分が遺言者の真意であって、これを方式違背として無効とし、元の部分を有効とすることが、必ずしも遺言者の真意に適うとはいえないケースもあるようです。
財産目録の加除・訂正その他の変更の方法
- 遺言書に添付する財産目録の加除・訂正についても遺言書本文の加除・訂正の方法と同様です。
- 具体的には、財産目録中の記載の一部を訂正する場合には、適宜の方法で訂正したうえ、「本目録第○行目中、○字削除○字加入」などと訂正箇所を指示する旨をして署名し、訂正箇所に押印する必要があります。
- 財産目録を差し替える方法で、遺言書を変更することもできます。この場合も、上記と同様の方法で行う必要があります。
- たとえば、旧目録を斜線などで抹消したうえで、その斜線上に抹消印を押し、新目録の紙面上に追加印を押したうえで、これを添付し、さらに本文が記載された紙面上に訂正文言(たとえば、「旧目録を削除し新目録を追加した。」)を記載し、遺言者自ら署名する必要があります。
- 単に古い財産目録と新しい財産目録等を差し替えて、あたかも当該遺言の作成時から差し替え後の財産目録が添付されていたかのような遺言書を作出することは想定されていません。
財産目録を添付する場合の特則
- 自筆証書遺言に、これと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録について自書することを要しません(自書要件の緩和)。その場合、遺言者は、同目録の毎葉(自書によらない記載が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
- 財産目録については、各ページに遺言者の署名押印が求められているほかは、特段の方式は定めれられていません。遺言者本人がパソコンなどにより作成したものはもちろん、他人が代筆しまたは他人がパソコンなどにより作成したものでも差し支えなく、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを利用することもできます。
- 添付する財産目録については、本文の用紙とは別の用紙に作成する必要があります。たとえば、パソコン印字した財産目録の上部余白に遺言書本文(「これは長男に相続させる」など)を自書して遺言書としても、遺言としての効力を生じません。
- 財産目録への押印については、遺言書本文に押印された印と同一のものでなくてもよく、遺言書の本文部分と財産目録との間に契印がなくても差し支えありません。
総説
総説
- 従来、自筆証書遺言に係る遺言書は、遺言者自らがその保管・管理をすべきものとされてきましたが、平成30年の民法改正に合わせて、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管および情報の管理を行う制度を創設しました。
- その保管に係る遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないとするなどの措置を講じた「法務局における遺言書の保管などに関する法律」、いわゆる遺言書保管法が令和2年7月10日から施行されました。
- これにともない、自筆証書遺言に係る遺言書については、遺言者自らが保管するか、または法務局に保管してもらうかを任意に選択することができるようなりました。
遺言書の保管の申請
- 遺言書保管法にもとづき、法務局における保管の対象となるのは、民法の規定にもとづく自筆証書遺言に係る遺言書のみです。
- 遺言者は、その所在地、本籍地または遺言者所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局または地方法務局の本局および支局)に自ら出頭して、遺言書保管官に対し、自筆の遺言書(法務省令で定める様式にしたがって作成した無封のもの)の保管を申請することができます。
- 遺言書の様式については、A4用紙を用い、所定の余白を設け、縦置きまたは横置きあるいは縦書きまたは横書きのいずれかを問わず、片面のみに記載してページ番号を記載すること、数葉にわたる場合でもとじ合わせないこととされています。遺言書の本文は、必ず遺言者が自書し、作成年月日を自書し、次は署名押印します。
- 保管の申請は、遺言者本人が自ら出頭して行います。代理人による申請は認められません。保管の申請にあたっては、遺言書に添えて① 遺言書に記載された作成年月日、② 遺言者の氏名、生年月日、住所および本籍(外国人は国籍)、③ 受遺者・遺言執行者の記載があるときは、その氏名または名称および住所、④ その他法務省令で定める事項を記載した申請書を提出し、また、上記②の事項を証明する書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)その他法務省令で定める書類を添付しなければなりません。
遺言書保管官による本人確認および方式適合性などの確認
- 遺言書保管官は、保管申請があった場合、申請人に対し本人確認のために必要な書類(個人番号カードや運転免許証など)の提示もしくは提出または説明を求めるものとされています。
- 遺言書保管官は、提出された遺言書が、民法に規定する自筆証書遺言の方式に適合するか否かについて、外形的な確認を行います。
- 具体的には、提出された遺言書について、作成日付けおよび遺言者の氏名の記載、押印の有無、本文の部分が手書きで書かれているか否かなどの確認を行うとともに、出頭した遺言者に当該遺言書を自書したことの確認が行われます。
- 遺言書保管官は、遺言書の内容の適法性、有効性についての審査権限を有しません。したがって、遺言書の保管が受理されても、当該遺言の実態法上の有効性が確認されたわけではありません。
遺言書の保管および情報の管理
- 遺言書は、遺言書保管所において保管され、遺言書保管官は、保管する遺言書について管理を行います。
- すなわち、遺言書保管官は、磁気ディスクをもって調整する遺言書保管ファイルに遺言書の画像情報のほか、遺言書作成の年月日、遺言者の氏名、住所および本籍など、所定の事項を記録することによって、情報の確認を行うのです。
- 遺言書保管官は、遺言書の保管にあたり、遺言者に対し、保管証を交付します。
遺言書の閲覧および保管申請の撤回
遺言書の閲覧および保管申請の撤回
- 遺言者は、自己の遺言書を保管している遺言書保管所(以下「特定遺言書保管所」という)に自ら出頭して、いつでも遺言書原本の閲覧を請求することができ、また、全国どこの遺言書保管所でもモニターによる遺言書の画像などの閲覧を請求することができます。
- 遺言者は、特定遺言書保管所に自ら出頭して、いつでも遺言書の保管の申請の撤回(遺言書の返還請求)をすることができ、その場合、遺言書保管官は、当該遺言書を返還するとともに、その遺言書に係る情報を消去しなければなりません。
- 遺言者は、撤回遺言によって当該遺言を撤回することができ、また抵触遺言その他の抵触行為によって、遺言の撤回が犠牲されるとの民法上の規律は、遺言書保管制度の利用の有無にかかわりません。
- 他方、保管申請の撤回(遺言書の返還請求)は、遺言自体の撤回ではなく当該遺言の効力がなくなるわけではありませんので、当該遺言そのものを撤回しようとするときは、撤回の遺言をするか、あるいは返還された遺言書の破棄などが必要です。
遺言書保管事実証明書の交付
- ある者の遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かについては、その者の死亡後に限り、近くの遺言書保管所に出向いて、自己が相続人、受遺者、遺言執行者など(以下「関係相続人など」という)に該当する遺言書(以下「関係遺言書」という)の保管の有無を調べることができます。
- 保管の有無ならびに関係遺言書が保管されている場合には、遺言書作成の年月日および遺言書保管所の名称および保管番号を証明した「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。
- この請求は、請求書に遺言者の氏名および関係相続人などであることを証する戸籍事項証明書および住所証明書などの書面を添付して行います。
- 交付請求の結果、遺言者として特定された者が作成した遺言書が保管されており、かつ、その遺言書が請求者にとって関係遺言書に該当する場合には、遺言書保管事実証明書が交付されます。
- それ以外の場合、たとえば、遺言者として特定された者が作成した遺言書が保管されていない場合には、遺言書が保管されていない旨の証明書が交付されます。
遺言書情報証明書の交付または関係遺言書の閲覧
- 遺言書の保管を申請した遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者などの関係相続人などは、その遺言者の死亡に限り、遺言書保管官に対し、関係遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。この請求は、当該遺言書が保管されている遺言書保管所以外の遺言書保管所に対しても行うことができます。
- 請求にあたっては、請求書に遺言者の死亡の事実およびその相続人の範囲を明かにすることができる戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類一式または法定相続情報一覧の写し、相続人の住所を証明する住民票の写しなどを添付します。
- 関係相続人などは、遺言者の死亡後に限り、関係遺言書を保管している遺言書保管所に対し、関係遺言書の閲覧を請求することができます。遺言書そのものの返還請求はできません。
- なお関係相続人などは、遺言者が死亡している場合に限り、遺言書の画像を含む遺言書保管ファイルの記録事項をモニターに表示する方法での閲覧を請求することができます。
- 遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し、または関係遺言書の閲覧をさせたときは、関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人ならびに受遺者および遺言執行者(これらの者がすでに知っているときを除く)に通知します。
- 遺言書の保管の申請や証明書の交付を請求する場合には、所定の手数料を納める必要があります。
- 相続手続きは、「遺言書情報証明書」を添付して行います。遺言書と同一の効力を有します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは
- 公正証書遺言は、原則として遺言者が公証役場へ出向き、証人二人以上の立ち会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述の内容を証書に記載して、これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者および証人ならびに公証人が署名押印して作成するものです。
- 遺言者が、病気などで公証役場に出向くのが難しいときは、公証人が遺言者宅や病院、介護施設などに出張して作成することができます。
- 遺言公正証書については、家庭裁判所の検認を要しません。
公正証書遺言の作成方法
- 公正証書遺言は、① 証人二人以上が立ち会い、② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、④ 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、各自がこれに署名押印したうえ、⑤ 公証人が法定の方式にしたがって作成した旨を付記して、署名押印することにより成立します。
- 口授とは、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることをいいますから、高齢や病気などで字を書くことが難しい方であっても、遺言の内容を公証人に口授することができれば、公正証書遺言を残すことができます。また、遺言者が手の震えなどで署名ができないときは、公証人がその事由を付記して遺言者の署名に代えることができます。
- 在日外国人も我が国の方式にしたがって遺言をすることができますが、公正証書遺言は日本語で作成されますので、日本語を解せない場合には、通事(通訳)の立ち会いが必要です。
- また、在外日本人は外国法の認める方式により遺言をすることができるほか、我が国の方式にしたがって遺言をすることができ、その場合、公正証書遺言における公証人の職務は我が国の在外領事が行います。
聴覚・言語機能障害者に関する特則
- 公正証書遺言については、口がきけない方や耳が聞こえない方も遺言ができるようにその特則が定められています。
- すなわち、口がきけない方が公正証書遺言をする場合には、遺言者は公証人への口述に代えて、遺言の趣旨を翻訳人に通訳(手話など)により申述し、またはその内容を自書して公証人に伝えることができます。
- また、耳が聞こえない方に対しては、公証人は遺言者への読み聞かせに関して、遺言者の口述を筆記した内容を通訳人の通訳(手話など)により伝えることができます。
- 公証人は、この特則により遺言書を作成した場合には、その旨を付記しなければなりません。
- 通訳人の通訳としては手話のほか、その種類を問わず、その資格も特に定められていません。裁判例として、約9年間にわたって遺言者の介助にあたり、意思疎通をはかってきた実績をもつ者に、通訳人としての的確性を認めたものがあります。
- さらに公証人は、公正証書遺言一般について、遺言者および証人に対し、遺言者の口述内容の承認を求める方法として証書の読み聞かせのほか、閲覧させる方法によることができます。口がきけない方や耳が聞こえない方の場合には、遺言者が公証人との筆談により、遺言の内容を伝え、公証人が筆記した証書を閲覧させる方法によることができます。
公正証書遺言の実際
- 公証実務では、遺言者がいきなり公証役場を訪れてその場でただちに公正証書を作成するということではありません。
- まず公証人が、遺言者本人またはその依頼を受けた者から遺言の内容を聴取し、あるいは下書き・メモなどなどの交付を受けたうえで、公正証書の原案を作成しておきます。
- そして、事前に約束していた日時に遺言者と証人二人が公証役場に出頭し、その立ち会いのもとで、遺言者から遺言の趣旨の口授を受け、その内容があらかじめ筆記したところと同一であることを確認し、あるいは必要に応じて加筆修正します。
- これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者および証人が間違いないと承認したところで、各自が署名押印し、最後に公証人が民法所定の方式にしたがって、作成したことを付記して署名押印をする手順で進められるのが通例です。
- 遺言公正証書の作成にあたって、公証人は、遺言者本人であることの確認を要するほか、相続人や受遺者、遺言の対象となる財産などを確認し、あるいは手数料の算定資料とするため、通常、遺言者本人の印鑑証明書と実印、本人と相続人との関係を証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)、受遺者の住民票の写し、登記事項証明書や固定資産評価証明書などの提出を求めています。
証人の立ち会いの意義
証人の立ち会いの意義
- 公正証書遺言をするには、証人二人以上の立ち会いを要することが、民法で定められています。
- 証人は、遺言者が本人であること、遺言者が自己の意思にもとづいて遺言の趣旨を公証人に口授したこと、公証人の筆記が正確であることなどを確認するのがその任務です。
- 証人の立ち会いによって遺言者の真意を確保し、後日の紛争を未然に防止しようとするものです。
証人適格
- 証人の資格について、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は証人となることができないと規定しています。
- 証人欠格者が遺言の内容に利害関係を有するか否かに関わりなく、欠格者が証人となって作成された遺言書は無効です。
- 推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者、すなわち遺言書の作成時において、第一順位の相続人となるべき地位にある者をいいます。遺言執行者は、当該遺言の受益者ではないので、証人適格を有します。目が見えない者の証人適格については、これを肯定するのが判例の立場です。
- 遺言者の兄弟姉妹はどうでしょうか。
遺言者の推定相続人が配偶者と子である場合には、遺言者の兄弟姉妹やその配偶者および直系血族(甥姪など)は、遺言者の直系血族に該当しませんので証人となることができます。
- 遺言者の推定相続人が、配偶者と兄弟姉妹である場合には、当該兄弟姉妹はもちろん、その配偶者および直系血族(甥姪など)も証人となることはできません。
- 推定相続人が配偶者と直系尊属である場合も、配偶者の兄弟姉妹およびその子は、推定相続人である直系尊属の直系血族に該当しますので証人となることはできません。
- 証人適格は、遺言時において有すれば足ります。たとえば、子Aがいる場合に遺言者の弟Bを証人の一人として遺言書を作成し、その後Aが死亡し、その代襲者および直系尊属もないため、Bが推定相続人となったとしても、遺言の効力に影響はありません。
証人の立ち会いの有無
- 証人は、公正証書の手続き中、そろって最初から最後まで立ち会っていなければなりません。
- 判例は、証人の一人がすでに遺言内容の筆記が終わった段階から立ち会ったもので、その後、公証人が読み聞かせたのに対し遺言者がただうなずくのみで、口授あったとはいえず証人が遺言者の真意を十分確認することができなかった場合には、民法所定の方式に反し、無効であるとしています。
- 他方で判例は、遺言者が署名押印をする際も立ち会うことを要するが、いったん証人二人の立ち会いで筆記を読み聞かされて署名し、短時間後に証人一方の立ち会いで再度読み聞かされて押印し、他方の証人は直後に押印を確認したという場合(押印には立ち会わず)、遺言の効力を否定するほかはないとまでは言えないとしています。
不適格者が同席していた場合
- 遺言公正証書作成の際、法定人数の証人が立ち会っていたものの証人不適格者が同席していた場合については、問題です。
- 判例は、民法所定の証人が立ち会っている以上、不適格者によって遺言の内容が左右されたり遺言者が自己の真意にもとづいて遺言をすることが妨げられたりするなど、特段の事情がない限り遺言が無効となるものではないとしています。
しかしながら、不適格者の同席は避けるのが相当といえるかと思います。
遺言者の口授の意義
遺言者の口授の意義
- 公正証書遺言の場合、遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人は遺言者の口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
- 口授とは、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることをいいます。言語を発してすることを要します。
- 疾病のため言語が不明瞭となった者に対し、公証人が質問を発し遺言者が仰臥したままわずかに動作で答えたという事案があります。判例は、遺言者が公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定または否定の挙動を示したに過ぎないときは、口授があったとはいえない、としています。
- 証人の一人が、公証人による遺言内容の筆記が終わった段階から立ち会い、その後公証人が筆記内容を読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった場合には、口授があったとはいえないとしています。
- 遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し、手を握り返したに過ぎないときは、口授があったとは認められません。
- まったく音声をともなわない「身ぶり」や「しぐさ」などの身体的挙動は、口授とはいえないでしょう。
実務上の口授
- 民法上、遺言者の口述 → 公証人による筆記 → 読み聞かせまたは閲覧 → 遺言者・証人の承認および署名押印という順序が定められています。しかし、実際上、事前の相談で遺言者やその依頼を受けた者から聴取した内容や交付されたメモなどにもとづき、公証人が原案を作成しておき、遺言当日証人立ち会いのもとで遺言者から口述を受けます。
- そして、同趣旨の口述であることを確認し、必要に応じて加筆修正したうえで読み聞かせまたは閲覧させるなどの順序を踏むのが少なくないと思われます。
- この取り扱いは、事前に戸籍事項証明書や受遺者の住民票の写し、登記事項証明書などの提示を求めるのとあわせて、遺言の内容の正確性を期すものとして、その合理性が存するものと考えられます。
- この点に関し判例は、次のように判断しています。
妻子と別れて乙女と同棲している甲が、入院中の自分に代わって乙を公証役場に赴かせ、自己所有の不動産を妻子および乙の4名に均等に分与するという遺言の趣旨を伝えさせました。公証人は、乙から聴取した遺言の内容をあらかじめ公正証書用紙に清書したうえで、遺言当日、遺言者および証人に読み聞かせたました。
- そして、遺言者は「この土地と家は皆のものに分けてやりたかった」旨を述べ、これを承認して署名押印した事案につき、当該遺言が口授と筆記および読み聞かせが前後したにとどまるのであって、遺言者の真意を確保し、その正確を記するため遺言の方式を定めた法意に反するものでないから、民法所定の方式に違反するものではないとしています。
- 公証人があらかじめ他人作成のメモにより、公正証書作成の準備として筆記したものにもとづいて、遺言者の陳述を聞き、その筆記を原本として公正証書を作成した場合であっても、当該事実関係の下においては、口授の要件を欠くものとはいえないとしました。
- 入院中の遺言者が、妹に遺言内容を伝え、妹が筆記した書面の交付を受けた者が、公証人にこれを伝え、公証人が公正証書用紙にあらかじめ清書したうえで、病室を訪れて、清書した遺言書にもとづいて遺言者・証人に読み聞かせ、遺言者に対し遺言内容に相違ないかを確認した事案につき、遺言者の真意は一応確保されており、口授の点において方式に違背するとはいえないとした裁判例があります。
口授を認めた事例
口授を認めた事例
- 公証人が事前に、遺言者本人または遺言者の依頼を受けた第三者から遺言内容を聴取し、あるいは遺言内容を記載した原稿の交付を受けて、証書の原案を作成しましたが、公証人が改めて遺言者との間で、遺言の内容について口頭で確認を行いました。
それによって準備した証書の原案の内容が、遺言者の意思と一致することを確かめたうえで、読み聞かせを行なって公正証書を作成したときは、民法所定の方式に欠けることはありません。
- 公証人は、弁護士が遺言者から聴取した事項を記載した書面の送付を受けて、遺言書案を作成したうえ、当日、入院先でこれを遺言者に交付しました。
そして、各項目ごとに読み聞かせて、その内容が遺言者の真意に合致することを確認し、条項中の相続人の氏名の誤記について、遺言者から訂正の申し入れを受けた場合は、遺言の趣旨の口授を受けたといえるのであって、遺言は有効と認められます。
口授を認めなかった事例
- 遺言者が、公証人が用意していた書面を読み上げ、図面を示してその内容を確認したことに対し、「それでよい」といっただけの場合には、遺言者が当該書面や図面の作成に自ら関与するなどして、遺言の内容について十分承知していたと認められる特段の事情がない限り、口授があったとはいえません。
- 遺言者の自宅土地建物などを、同居していた女性に遺贈することなどを内容とする公正証書遺言につき、遺言者が事前に遺言の内容を公証人に説明したことはありませんでした。
そして、公正証書作成時も、公証人が問いかけたのに対し、声を出してうなずいたのみであったことから、遺言者が遺言の趣旨を口授したとは認められないとした事例があります。
- 公証人が事前に、遺言者の長男から示された遺言案が遺言者の意思に合致しているのか直接確認していないこと、遺言当日も公証人が病室で横になっていた遺言者に遺言公正証書案を見せながら、項目ごとにその趣旨を説明し、それでよいかどうかの確認を求めました。
これに対し、遺言者は、うなずいたり「はい」と返事をしたのみであること、遺言の内容が多額かつ多数、多様な保有遺産を、相続人全員に分けて相続させることを主な内容とするものであることなどの事実関係のもとでは、口授があったとはいえないとされた事例があります。
- 遺言者は、公証人が、遺言案を読み上げて内容の確認をしたところ、うなずくのみでその内容を具体的に発信することはなく、同人が自ら発した言葉自体により、公証人および証人が遺言の趣旨を理解できるように口授したものとは認められないとした事例、があります。
公証人の筆記、読み聞かせまたは閲覧
- 公証人は、遺言者の口述を筆記してこれを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
- 公証人の筆記は、遺言書の面前でなくてもよく、パソコンなどを使用して行われるのが一般的です。実際には、事前の相談内容や交付を受けたメモなどにもとづき、あらかじめ原案を作成しておきます。
- そして、当日、証人立ち会いのもと遺言者から口授を受けて、原案と同趣旨の口述であることを確認し、必要に応じて加筆修正したうえ、読み聞かせまたは閲覧させるという順序を踏むものが少なくありません。
遺言者・証人の署名
遺言者・証人の署名
- 遺言者と証人は、公証人から遺言公正証書の読み聞かせを受け、またはこれを閲覧して、その筆記が正確なことを承認したのち、各自証書に署名し押印しなければなりません。
- 遺言者の署名は必ずしも戸籍上の氏名であることを要せず、芸名、ペンネームであっても、本人の同一性が識別できるものであればよいと解されていますが、公証実務では本人確認のために印鑑証明書の提出が求められていますので、それらに記載された氏名で署名します。
- 普段「國」を「国」、「實」を「実」などと記載している方は、普段使用している文字で差し支えありません。
- 裁判例には、遺言者の署名は記載内容の正確性を承認する意味が大きいことから、氏名の最初の一文字は読めるが、以下は判読不可能でも遺言者が自己の氏名として署名したことが明らかであれば、有効であるとしたものがあります。
- 遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。事由の記載は、病気や手の震え、無筆などの簡潔な記載で足り、また、公証人が代署することは法律上の要件ではありません。しかし、公証実務上は「遺言者は病気のため署名ができないので、本公証人が代わって署名する旨を付記したうえ、氏名を代署するのが通例とされています。
- 遺言者が「署名することができない場合」には、まったく署名が不可能な場合のほか、それによって症状が悪化するような場合が含まれます。署名の可否の判断は、公証人の合理的裁量にまかされています。
- これについて、判例には、遺言者自らが署名するについて格別支障があったとは認められず、公証人の代署を方式違背として無効としたものがあります。
- 証人については、自ら署名することが必要であり、代署はできません。なお、証人に対する本人確認は、適宜の方法で足ります。
遺言者・証人の押印
- 遺言者の用いる印鑑は、実印に限ります。公証人は、遺言者が人違いでないことの確認を要するため、印鑑証明署の提出を求め、実印を用いて押印するのが通例です。
- 証人については、押印は実印を用いる必要はありません。
- 押印は公証人の面前で、本人に依頼されたもの(公証人を含む)が代わってしても差し支えありません。
- 外国人については、法令上、署名押印が求められている場合には、外国文字による署名のみをもって足りるとされています。
公証人の署名・押印
- 公正証書遺言について、最後に公証人が、証書は民法の方式にしたがって作成した旨を付記し、これに署名押印することによって公正証書遺言が作成され成立します。
- 口がきけない者または耳が聞こえない者について、公証人が民法の定める方式にしたがって公正証書を作成したときは、その旨を当該証書に付記しなければなりません。裁判例は、遺言公正証書中に民法の規定にもとづき作成したことを明記したことがなくても、全体としてその民法の方式にしたがって作成されたことが明瞭に読み取ることができる場合には、その要件に欠けることはないとしています。
公証人法所定の事項の記載
公証人作成の公正証書には、① 証書の番号、② 嘱託人または代理人の住所・職業・氏名・年齢、③ 公証人が嘱託人または代理人の氏名を知り面識があるときはその旨、④証明書の提出その他確実な方法によって人違いでないことを証明させたこと、⑤ 通事(通訳)または立ち会い人を立ち合わせたときは、その旨および事由ならびに通事(通訳)または立ち会い人の住所・職業・氏名・年齢、⑥ 作成の年月日および場所などを記載しなければならないとされています。
遺言公正証書の保管
- 遺言公正証書の原本は、作成した公証役場に保管され、遺言者には通常その正本と謄本の各一通が交付されます。
- 相続人またはその承継人、利害関係人などは遺言公正証書の正本・謄本が見つからない場合には、遺言者の死後に限り当該遺言公正証書を保管している公証役場に対し、遺言者の死亡および相続人であることを証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)、請求者の運転免許証などの本人確認書類などを提示してその閲覧または謄本の交付を請求することができます。
- 亡き甲の相続人である乙について、甲が遺言公正証書を残しているかどうかを調べることができます。相続人乙は、甲の死亡後に限り、全国どこの公証役場でも照会することができます。乙は近くの公証役場に出向いて、甲が遺言公正証書を残しているかどうかを調べることができます。この場合、遺言者の死亡および相続人であることを証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本、運転免許証)などの本人確認書類などの提示を要します。
- 出向いた公証役場において、申出にかかる遺言公正証書の存在が判明したときは、申出人に対し、当該遺言公正証書を作成した公証役場名などを知らせます。
- 申出人らは該当の公証役場に出向いて、当該遺言公正証書の閲覧または謄本の交付を請求することができます。
- 他方、申出にかかる遺言公正証書に該当するものがなかったときは、申出人に対し、その旨が回答されます。
概念
概念
- 秘密証書遺言は、① 遺言者が遺言署を作成し、これに署名押印したうえ、② その遺言書を封紙に封入して、遺言書に押した印で封印し、③ 遺言者がその封書を、公証人および証人二人以上の前に提出して、自己の遺言書であることおよび氏名・住所を述べ(代筆の場合は筆記者の氏名・住所を)、④ 公証人が遺言書の提出日付および遺言者の口述を封紙に記載し、遺言者、証人および公証人が封紙に署名押印して作成するものです。
- 封紙で閉じた遺言書は遺言者に返還され、遺言者において保管します。遺言者の死亡後に、家庭裁判所において、その開封および検認の手続きが必要です。
遺言書の作成
- 秘密証書遺言の作成方法については、遺言者の署名押印が規定されているのみです。遺言者の署名押印があれば、本文は自筆(手書き)であることを要しませんので、パソコンを操作して作成したものでも、他人が代筆し、または他人がパソコンで作成したものでも差し支えありません。
- 日付の記載も要求されていません。日付を記載しても構いませんが、後日提出を受けた公証人が封紙に日付を記載しますので、その日付が、遺言能力の有無および遺言の先後の判定基準となります。
- 遺言者の署名は、自分でしなければならず、署名がない場合は、方式違反として無効になります。したがって、署名ができない者は、この方式によることはできません。押印については、実印・認印などのいずれでも差し支えありません。
- 遺言者は作成した遺言書を封入したうえ、遺言書に押した印で封印しなければなりません。
封書の提出および申述
- 遺言者は、遺言書の入った封書を公証人および証人二人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨ならびに筆者の氏名および住所を申述しなければなりません。公証人に対する申述は遺言者自らが行います。
- 筆者とは、遺言内容の記載という事実行為を行った者をいいます。遺言者が自ら筆記(自書またはパソコンによる印字)した場合には、その旨を申述すれば足ります。遺言者以外の者が遺言書を筆記した場合には、その氏名および住所を申述しなければ、その遺言書は無効になります。
- 判例は遺言者以外の者が、市販の遺言書の書き方の文例を参照し、ワープロを操作して、文例の遺言者などの氏名を当該遺言の遺言者などの氏名に置き換え、その余は文例のまま表題および本文を入力したうえで印字し、遺言者が署名した事案につき、次のように述べています。
- すなわち、ワープロを操作して遺言書の表題および本文を入力し印字した者が、民法上の筆者にあたり、遺言者は公証人に対し、筆者として印字者の氏名および住所を申述しなかったから、民法所定の方式を欠き無効であるとしています。
- 口がきけない方が、秘密証書によって遺言を遺言をする場合、遺言者は公証人および証人の前で、その証書は、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して申述に代えることができます。
- 裁判例として封紙への自書につき、筆者の氏名および住所の一部を欠く場合でも、遺言書全体の記載などから筆者が明確に特定されれば、有効としたものがあります。
公証人の記載
- 秘密証書遺言は、公証人が、遺言書の提出日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち、遺言者および証人とともに署名押印することで成立します。
- 証人はもちろん遺言者も自ら署名することを要します。署名ができない場合には、秘密証書による遺言はできません。
- 封紙付きの遺言書は、遺言者に返還されます。封紙は、遺言書が封入されていることを公証するもので、その内容を公証するものではありません。
方式に欠ける秘密証書遺言の効力
- 秘密証書遺言が、その方式に違反し、無効となる場合でも自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有します。
- 自筆証書遺言の方式は、その全文および日付の自書、署名および押印を備えていることであり、これが守られていれば、秘密証書遺言としては無効であっても(たとえば、封印が遺言書に押印したものと異なるとき)、なお自筆証書遺言としてその効力を有します。
概念
概念
- 特別方式による遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言の二つがあります。さらに、危急時遺言は① 死亡危急時遺言と、② 船舶遭難者遺言に分かれます。隔絶地遺言は、① 伝染病隔離者遺言と、② 在船者遺言に分かれます。
- 特別方式による遺言は、普通方式による遺言が困難または不可能な特別の事情に限って、より簡易な方式として認められています。したがって、遺言者が普通方式による遺言ができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を失います。
遺言書の作成
- 秘密証書遺言の作成方法については、遺言者の署名押印が規定されているのみです。遺言者の署名押印があれば、本文は自筆(手書き)であることを要しませんので、パソコンを操作して作成したものでも、他人が代筆し、または他人がパソコンで作成したものでも差し支えありません。
- 日付の記載も要求されていません。日付を記載しても構いませんが、後日提出を受けた公証人が封紙に日付を記載しますので、その日付が、遺言能力の有無および遺言の先後の判定基準となります。
- 遺言者の署名は、自分でしなければならず、署名がない場合は、方式違反として無効になります。したがって、署名ができない者は、この方式によることはできません。押印については、実印・認印などのいずれでも差し支えありません。
- 遺言者は作成した遺言書を封入したうえ、遺言書に押した印で封印しなければなりません。
死亡危急時遺言
- 疾病その他の事由で、死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときに用いられる特別の方式を、死亡危急者遺言といいます。
- この方式で、死亡の危急に迫った者が遺言をするには次の要件を満たす必要があります。
すなわち、① 証人三人以上の立ち会いで、② その一人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた証人がこれを筆記し、③ 筆記した証人が、これを遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ、④ 各証人が筆記の正確なことを承認し、署名・押印することにより遺言が成立します。
- 死亡危急者遺言は、遺言者が死亡の危急にある場合に利用できますが、医師により危篤状態と診断されている必要はなく、疾病その他相当の事由があって、遺言者自身が死亡の危急に迫っていることを自覚している場合には、この方式によることができます。
- 口授の方法は公正証書遺言に準じますので、遺言者が遺言の趣旨を口授する能力がなければ遺言は無効になります。裁判例として、遺言書の作成当時において、遺言者には意識障害があって、遺言能力がなく、遺言する意思もなくかつ、口授の要件を欠き、無効であるとしたものがあります。
- 死亡危急者遺言は、当該遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人(相続人、受遺者、遺言執行者など)から家庭裁判所に請求して、その確認を得なければ効力を生じません。
- 家庭裁判所の確認は、遺言者の真意にもとづくものか否かを判断するものであり、家庭裁判所は遺言者の真意に出たものとの心証を得なければ、確認の審判をすることができません。
船舶遭難者遺言
- 船舶が遭難しその船舶中で死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときに用いられる特別の方式を船舶遭難者遺言といいます。
- この遺言書の作成には、証人は二人以上であればよく遺言は口頭で行い、証人は危難が過ぎてから遺言書を作成し、署名押印すれば足ります。
- この遺言は証人の一人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所の確認を得なければなりません。
伝染病隔離者遺言
- 伝染病隔離者遺言は、伝染病のために隔離された者が作成する遺言で、警察官一人と証人一人以上の立ち会いで、遺言書を作成することができるものです。
- 伝染病隔離者に限らず、刑務所内にいる者、地震や洪水による交通遮断など、一般社会との交通が法律上または事実上自由になしえない場所にある者が対象になります。
在船者遺言
- 船に乗っている者が遺言書を作成するときは、船長または事務員一人と証人二人以上の立ち会いで、遺言書を作成することができます。
- 航空機内にある者についても類推適用されます。
特別方式による遺言の失効
- 特別方式による遺言は、簡易な方法による遺言書の作成を認めたものですので、普通方式による遺言が可能であれば、特別方式によることは認められません。
- そこで、特別方式による遺言が認められた場合であっても、その後普通方式による遺言ができるようになってから6ヶ月間生存するときは、特別方式による遺言は失効するものとされています。
- 裁判例として、遺言者が危急時遺言ののち、危篤状態を脱して1年以上生存していた事案につき、遺言者に自書能力がなくても公正証書は可能であったから当該遺言は、普通方式による遺言が可能となったときから6ヶ月間経過したものとして、無効としたものがあります。
遺言の効力の発生時期
遺言の効力の発生時期
- 遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じます。遺言に停止条件が付され、その条件が遺言者の死亡後に成就した場合には、条件が成就したときから、効力を生じます。
- この場合、遺言者が条件成就の効果に遡及効を与えているときは、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。他方、停止条件が遺言者の死亡前に成就していれば、遺言は無条件となり、遺言者の死亡時から効果を生じます。
- 遺言の内容が一定の手続きを得ないと、効力が生じない場合には、その要件を具備しなければ効力を生じません。たとえば、遺言による推定相続人の廃除については、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、廃除の審判が確定することにより、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。
- 遺言は、遺言者の死亡によってはじめて効力を生じ、また、遺言者はいつでも遺言を撤回することはできますので、遺言者の死亡までは遺言によって利益を受ける者とのあいだに何らの法律関係も生じません。
- 判例は、受遺者とされた者は、単に遺言が効力を生じたときは、遺贈の目的物である権利を取得できる事実上の期待を有する地位にあるにすぎないから、遺言者の生存中、推定相続人などが遺言の無効確認の訴えを提起することは許されないとしています。
- また、遺言者の生存中は、遺贈を原因とする仮登記をすることはできません。学説上も消極に対するのが多数です。事実上の期待を有するにすぎないとする判例の立場にしたがえば、受遺者の仮登記請求権を肯定するのは困難であると考えられます。
遺言の解釈
- 遺言はどのような効力を生ずるかは、もっぱら遺言に示された遺言者の意思解釈(遺言の内容を明確にすること)によって決せられます。通常、遺言書に記載された文言にもとづき、遺言者の意思を確定することになりますが、特に自筆の遺言書については、遺言書の文言のみで遺言者の意思を確定することが困難な場合があります。
- 判例は、遺言者の意思表示の内容は、その真意を合理的に探求し、できる限り適法有効なものとして解釈するべきであり、そのためには遺言書の文言を前提としながらも、遺言者が遺言書の作成に至った経緯およびそのおかれた状況などを考慮することも許されるとしています。
- 遺言書が多数の条項から成る場合には、そのうちの特定の条項の解釈にあたって、単に当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきものとしている裁判例があります。
- もっとも、遺言書記載の文言を離れ、およそ遺言の解釈においては遺言者の真意を探求すべきものとするのは相当でありません。遺言の解釈が必要とされるのは、遺言書の文言から一義的に確定することが困難な場合であると理解するのが相当であると考えられます。
- 遺言書の記載自体から、遺言者の意思が合理的に解釈できる場合には、遺言書にあらわれていない事情をもって遺言の意思解釈の根拠とすることは許されません。
- 遺言解釈の一般的な指針として、裁判例は、遺言書の記載自体から遺言者の真意が合理的に解釈しうる場合には、遺言書にあらわれていない遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などをもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないとしています。
- また、裁判例は、遺言書の記載自体から遺言者の真意が合理的に解釈しえない場合には、遺言書の記載の意味を知るために、遺言者がいかなる意味のものとしてその言葉を用いたかを明らかにする必要があり、そのためには、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などを考慮すべきであるとしています。
登記官の審査との関係
登記官の審査との関係
- 権利に関する登記の申請があった場合における登記官の審査は、原則として書面による審査に限られます。登記原因証明情報などとして遺言書が提出された場合、当該遺言書の解釈にあたっては、基本的には、遺言書の文言やその全記載から判断せざるをえません。
- 裁判例として、「姪にすべてまかせる」との文言につき、遺産の全部を姪に遺贈する趣旨の遺言として有効とした事例があります。これは、遺言者作成に至る経緯や遺言者と姪との従前の関係などを踏まえたものであり、登記官の審査との関係でいえば、遺贈の趣旨に解するのは難しいという考えもあります。
遺言者の意思の考慮
- 遺言の解釈にあたっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して、合理的にその趣旨を解釈すべきですが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが、意思にそうゆえんであり、そのためには遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯およびそのおかれた状況などを考慮することも許されるというべきである、という裁判例があります(最高裁判所判例 平成5年1月19日)。
- 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合に、そのうちの特定の情報を解釈するにあたっても、単に遺言書のなかから当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探求し、当該情報の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である、とした裁判例があります(最高裁判所判例 昭和58年3月18日)。
遺言の解釈事例(判例)
- 財産を「全部まかせる」旨の文言は、遺贈とは認められないとされました。
- 遺産を「公共に寄与する」旨の遺言につき、公共目的を達成できる団体などに遺贈する趣旨であり、遺言執行者に、受遺者として特定のものを選定することを委託する趣旨の遺言として、有効とされました。
- 「自由に裁量処分することを相続人Yに委任する」旨の条項につき、Yに「相続させる」趣旨と解すべきとした事例があります。
- 「遺言者所有の不動産『○○区7丁目60番4号』(住居表示番号のみ記載)を遺贈する」旨の遺言につき、遺言者の住所地にある土地・建物のうち建物のみを目的とするものと解することはできず、土地・建物を一体として遺贈したものと解すべきである、とされました。
- 遺言者の「私に万一のことがあれば、本件すべてを実弟Yにお渡しください」との文言を遺贈と解した事例があります。
遺言の無効
- 遺言は、公序良俗違反や強行放棄違反により無効とされる場合がありますが、遺産の全部を共同相続人中の一人に遺贈したからといって、公序良俗に反し無効であるとはいえません。
- この点については、主として不倫関係の維持などを目的とする遺贈の有効性が議論されています。たとえば、次のような裁判例があります。
「不倫関係の女性に全財産を遺贈する旨の遺言は、情交関係の継続をはかるためのものであるので、遺言者の妻の生活基盤をもおかし、社会一般的にも許されるものでなく、公序良俗違反で無効である」とされました。
- 遺言特有の無効原因として、方式違背、遺言能力の欠如、共同遺言、後見側の利益となる遺言があります。
遺言の取消し
- 財産上の事項に関する遺言については、他の法律行為と同じく、錯誤や詐欺・強迫による遺言は取り消すことができます。その取消権は、遺言者の相続人に承継されます。
- 錯誤を無効原因とした平成29年改正前の事案にかかる裁判例として、社会福祉法人が経営する養護盲老人ホームに入所していたものがした、同法人に財産全部を包括遺贈する旨の公正証書遺言につき、錯誤により無効としたものがあります。
総説
総説
- 遺言者は、その生存中いつでもその理由を問わずに遺言を撤回することができます。
- 遺言の撤回は、原則として前遺言を撤回する意思が遺言によって示されることを要しますが、遺言者自身がした法律行為や事実行為から、遺言と異なる意思の存在が推測されることによって、撤回が擬制されることがあります。
撤回遺言
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式によって、その遺言または一部を撤回することができますが、この撤回権は、あらかじめ放棄することはできません。遺言中に撤回権放棄の旨を記載した場合だけでなく、生前における遺言者・受益者間の撤回権放棄の合意も無効です。
- 遺言の撤回は、遺言の方式によるものでよく、前遺言と同一の方式によることは、要求されていません。すなわち、公正証書遺言をのちの自筆証書遺言で撤回すること、逆に自筆証書遺言をのちの公正証書遺言で撤回することができます。
- 遺言の記載として、「撤回する」あるいは「取り消す」という文言が使用されていなくても、撤回することがわかれば、撤回遺言として効力を有します。また、前遺言の特定が難しい場合には、「遺言者のした従前の遺言の全部を撤回する」の旨を記載すれば足ります。
- 実際には、単に遺言の全部または一部を撤回するだけでなく、従前の遺言の全部または一部を撤回したうえで、改めて新たな遺言をし、あるいは従前の遺言の内容を変更したり、追加したりする場合が少なくないでしょう。
撤回遺言
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式によって、その遺言または一部を撤回することができますが、この撤回権は、あらかじめ放棄することはできません。遺言中に撤回権放棄の旨を記載した場合だけでなく、生前における遺言者・受益者間の撤回権放棄の合意も無効です。
- 遺言の撤回は、遺言の方式によるものでよく、前遺言と同一の方式によることは、要求されていません。すなわち、公正証書遺言をのちの自筆証書遺言で撤回すること、逆に自筆証書遺言をのちの公正証書遺言で撤回することができます。
- 遺言の記載として、「撤回する」あるいは「取り消す」という文言が使用されていなくても、撤回することがわかれば、撤回遺言として効力を有します。また、前遺言の特定が難しい場合には、「遺言者のした従前の遺言の全部を撤回する」の旨を記載すれば足ります。
- 実際には、単に遺言の全部または一部を撤回するだけでなく、従前の遺言の全部または一部を撤回したうえで、改めて新たな遺言をし、あるいは従前の遺言の内容を変更したり、追加したりする場合が少なくないでしょう。
撤回の遺言文例
- 全部撤回の場合は、次のような文例になるでしょう。
遺言者は、令和○年○月○日○○法務局所属公証人○○○○作成令和○年第○○号遺言公正証書による遺言者の遺言の全部を撤回する。
- 全部撤回・新遺言の場合は、次のような文例になるでしょう。
遺言者は、令和○年○月○日○○法務局所属公証人○○○○作成令和○年第○○号遺言公正証書による遺言の全部を撤回し、改めて以下のとおり遺言をする。
- 一部撤回の場合は、次のような文例になるでしょう。
遺言者は、令和○年○月○日○○法務局所属公証人○○○○作成令和○年第○○号遺言公正証書による遺言者の遺言中、遺言者が下記建物を妻○○○○(生年月日)に相続させる旨の部分を撤回する。
撤回の擬制(法定撤回)
- 遺言者が、前遺言の内容と抵触する遺言をした場合、または遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合には、撤回の遺言書を作成するまでもなく、法律上当然に遺言を撤回したものとみなされます。これを法定撤回といいます。
- 前遺言と後遺言の内容の抵触として、次のような事例があります。
遺言者甲は、子Aに全財産を相続させる旨の遺言書を残していたが、これを失念して、後日子Bに全財産を相続させる旨の遺言書を作成した。この場合、Aに相続させる旨の前遺言は撤回したことになるのか問題です。
- 前事例で、両遺言の内容は抵触していますので、甲が前遺言の存在を失念していたとしても、のちにしたBに相続させる旨の遺言により、Aに相続させる旨の前遺言は撤回したものとみなされます。
- 民法は、「前の遺言がのちの遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、のちの遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定して、後遺言優先の原則を明らかにしています。ここにいう「抵触」とは、前遺言を執行させなければ後遺言の内容を実現することができない程度に内容が矛盾することをいいます。
- 抵触の有無は、遺言の解釈によって、その全趣旨から判断されます。裁判例として、第一遺言で全財産をAに相続させる旨の遺言をしたが、第二遺言でBに甲土地を相続させるほか、その余の遺産について、Bは指定相続分4分の1の割合で分割協議に参加しうるとする遺言をした事案があります。
- 判例は次のように述べています。
民法の「抵触」とは、両遺言の内容を実現することが客観的に不可能な場合のみならず、後遺言にいたった経緯など諸般の事情に照らして、前遺言と両立させない趣旨で、後遺言が成立された場合を含むと解するのが相当です。今回の事例は、遺言者は第一遺言と両立させない趣旨で第二遺言をしたものというべきであるから、両遺言は全面的に抵触しています。
- 他方、次のような裁判例もあります。
遺産をすべて妻に譲る旨の第一遺言をしたのち、妻の生存中は土地家屋その他一切の現状を維持し、妻の死後に換金して子らに一定の割合で与える旨の第二遺言をした事案につき、次のように判断しています。
- 第二遺言は第一遺言を前提として、妻の生存中は他の相続人から土地家屋などの売却や分割を求めないこと、妻死亡後は換価分割による代金を配分してほしいとの希望を述べたものと解すべきであるから、第二遺言は第一遺言と矛盾抵触しないと述べました。
- 遺言者が前遺言の存在や内容を失念して、これと抵触する遺言をしても前遺言は撤回したものとみなされます。
- 撤回とみなされるのは、後遺言と抵触する部分だけで、後遺言と抵触しない部分は有効の遺言として残ります。
遺言と抵触する生前処分
遺言と抵触する生前処分
- 遺言者が、遺言後にその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をしたときは、これらの行為によって当該遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。遺言と抵触する生前処分は、遺言者自身がしたものであることを要します。
- ここにいう「生前処分」とは、遺言者が遺言の対象となっている物や権利について、その譲渡や用益物件の設定をすること、特定債権の弁済を受けることなどをいいます。
- たとえば、「Bに甲土地を遺贈する」旨の遺言後、甲土地をCに売却した場合はこれに該当します。遺言者が前遺言の存在や内容を失念して、これと抵触する処分行為をした場合も遺言を撤回したものとみなされます。
- 生前処分によって遺言の撤回が擬制されるのは、当該生前処分の効力が生じていることが必要ですから、生前処分が無効であったり取り消されたりした場合には、撤回したものとはみなされません。
- また、遺言者が複数の不動産につき、遺贈の遺言をしたのち、その一部を第三者に売却し、または取り壊した場合、遺言者が生前処分にいたった事情や遺言者、受遺者および相続人の間の関係などを考慮し、遺言全体が撤回されたとはいえず、生前処分の対象とならなかった部分については有効としたものがあります。
- 遺贈の遺言と抵触する生前処分(売買)を原因とする所有権移転登記が「錯誤」を原因として抹消されている場合、当該遺言による遺贈を原因とする所有権移転の登記を申請することができます。
- 遺言者が、不動産を妻甲および長男乙に持分2分の1ずつ相続させる旨の公正証書遺言をしたが、甲が遺言者より先に死亡し、その後遺言者が持分2分の1を第三者に売却して所有権一部移転の登記をしたのちに死亡した場合には、当該遺言書を添付して遺言者の持分2分の1につき、乙への相続による持分移転の登記を申請をすることができるとした登記先例があります。
遺言と抵触する「その他の法律行為」
- 「その他の法律行為」とは、遺言後に当該遺言と抵触するその他一切の法律行為をいい、身分行為を含むものと解されています。
- 判例は、民法の「抵触」とは、単にのちの生前処分を実現しようとするときには、前遺言の執行が客観的に不能となるような場合にとどまらず、諸般の事情からのちの生前処分が前遺言と両立させない趣旨でされたことが明かである場合をも含むものと解するのが相当であるとしています。
- そして、終生の扶養を受けることを前提としてされた養子に対する遺贈の遺言後に協議離縁をした場合、当該遺贈はのちの協議離縁と抵触するものとして、撤回を認めています。
- 他方、裁判例には不動産を親族に遺贈する旨の自筆証書遺言後に、これを売却するため不動産業者との間で専任媒介契約を締結し更新したことが、遺言と両立させない趣旨でされたことが明かであることはいえないとして、抵触にあたらないとしたものがあります。
- 裁判例として、遺言者が養子に全財産を相続させる旨の遺言後に離縁していたところ、遺言者の死亡後、養子がした「遺贈」を原因とする所有権移転の登記の申請を却下した登記官の処分につき、次のように述べています。
- 本件遺言は、遺産分割方法の指定および養子の相続分を全部とする相続分の指定をしたものと認められ、また登記官は形式的審査権を有するにとどまり、遺言の趣旨を遺言者の記載から離れて考慮することはできず、その他遺贈と解すべき特段の事情があるとはいえないこと、さらに本件遺言は離縁により撤回したものとみなされるとして、登記官の処分は適法であるとしました。
故意による遺言者の破棄または遺贈目的物の破棄
- 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合(焼却、塗りつぶしなど)には、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。公正証書の場合には、原本が公証役場に保管されているので、遺言者に交付された正本または謄本の破棄だけでは撤回になりません。
- 遺言者が過失により遺言書を破棄したとき、あるいは火災などの不可抗力によって遺言書が消失し、または遺言者以外の者が破棄しても遺言の撤回には当たりません。
- これらの破棄の結果として有効な遺言の存在を認めることができない事態が生じますが、裁判例には、遺言者以外の者が遺言書を破り捨てた事案につき、次のように述べたものがあります。
- すなわち、当該遺言書が一部の共同相続人ら立ち会いのもとに、弁護士の手本および指示にしたがい作成され、その記録が弁護士の手元に保存されていたことから遺言の効力を認めたものがあります。
- 破棄には、焼却・破り捨てなど、遺言書の形状を破壊することだけではなく、抹消などにより、内容を判読できない程度にすることや遺言書の日付を判読不能にして遺言がいつ成立したのか不明にしたりすることも含まれます。
- 判例は、遺言者が自筆の遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで一本の斜線をひいた事案につき、次のように述べています。
- 赤色ボールペンで遺言書の文面全体に斜線をひく行為は、その一般的な意味に照らし、遺言書の全体を不要のものとし、そのすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされるとしています。
- 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、同様に、遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が遺贈の対象としたことを失念していたとしても、撤回の効力が生じます。
撤回された遺言の効力
- 遺言が撤回されたときは、遺言ははじめから存在しなかったのと同様の結果となりますが、遺言者が当該撤回行為をさらに撤回しまたはそれが効力を失った場合において、先に撤回した遺言が復活するのかという問題があります。
- この点につき、民法は、一旦撤回された遺言はその撤回の行為が撤回され、取り消され、または効力を失ったときでも、原則として、その効力を回復しないと規定しています。
- ただし、撤回行為が錯誤、詐欺または強迫を理由に取り消されたときは、撤回行為事態が遺言者の真意ではなく、復活を望む意思が明白であると考えられるため、最初の遺言が復活するものとされています。
相続させる遺言と特定財産承継遺言
相続させる遺言と特定財産承継遺言
- 従前、遺言実務、特に公正証書遺言において、特定の遺産を特定の相続人に相続させるものの遺言が多く用いられ、登記実務上もこの相続させる遺言により、特定の不動産を取得することとなった受益相続人が、単独で相続登記の申請をすることが認められてきました。
- その法的性質については、最高裁判所平成3年4月19日判決は、相続させる遺言は、遺言書の記載から、遺贈であることが明らかであるかまたは遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割方法の指定と解するのが相当です。
- かつ、これにより何らかの行為を要することなく、被相続人の死亡のときに、ただちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきであるとの判断を示しました。
- このように、相続させる遺言については、特段の事情がない限り、民法908条にいう「遺産の分割の方法」を定めたものと解されているため、遺産分割の方法の指定には本来の意味での遺産分割の方法を定めるもの(現物分割、代償分割など)と遺産分割の実行として特定の遺産を特定の相続人に取得させることを定めるものとが含まれることになります。
- そこで平成30年改正では、後者を「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言」とし、これを「特定財産承継遺言」と呼んでいます。
- もっとも、相続させる遺言については、上記最高裁判決が「遺贈と解すべき特段の事情がない限り」としているため、厳密には「遺産分割方法の指定としての相続させる遺言」と「遺贈」がありますが、基本的には平成30年改正法の規定する「特定財産承継遺言」にあたるものです。
特定財産承継遺言の類型
考えられる類型として、特定相続させる遺言、全部相続させる遺言、割合的相続させる遺言、精算型相続させる遺言、予備的相続させる遺言(補充遺言)などがあります。順次、説明いたします。
特定相続させる遺言
- 特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の特定相続させる遺言は、特定財産承継遺言の基本的な類型であって、遺言者が死亡して相続が開始すると同時に、遺産分割を経ないで当然に、特定の財産が特定の相続人に承継されます。不動産については、その権利を取得した受益相続人が、単独で相続による所有権移転の登記を申請することができます。
- 問題となるのは、相続人が複数いる場合において、遺言では「甲不動産をAに相続させる」とされているだけで、残余の財産の帰属について特に記載がない場合です。この場合、残余の財産については、遺産分割が必要になりますが、その前提として当該遺言の解釈が問題となります。
- すなわち、その解釈としては① Aに甲不動産を先取り的に取得させ、残余の財産はAを含む相続人全員に各自の法定相続分に応じて取得させる趣旨(甲不動産の取得は残余の財産の分割に影響しない)との解釈があります。
- さらに、② Aに甲不動産のみを取得させて、残余の財産は取得させない趣旨(残余の財産は他の共同相続人間で分割する)との解釈もあります。
- または、③ Aに甲不動産を含めて法定相続分により財産を取得させる趣旨(甲不動産の取得は特別受益として持ち戻すことになる)というものが考えられます。
- 相続分に応じた公平な配分という点から、③の趣旨に解される場合が少なくないと思われますが、遺言者の意思解釈の問題ですので、疑義を生じないよう、上記①の趣旨であれば特別受益もち戻し免除の意思表示をし、あるいは「その余の財産は全員の法定相続分にしたがって相続させる」として、その趣旨を明示し、上記②であれば「その余の遺産は甲以外の相続人に相続させる」などと工夫する必要があるでしょう。
- このように、遺言書に掲げられた特定の財産以外の財産についての記載がないと、遺産分割の協議をする必要があり、その場合、当該遺言の解釈が問題となります。
- これを避けるため、公正証書遺言の実務では「前各項に記載した財産以外の遺言者の有する動産その他一切の財産を遺言者の妻〇〇に相続させる」などと記載しておく例も少なくないようです。
特定相続させる遺言の文例
次のような文例が考えられます。
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の土地および建物を遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
(土地・建物の表示)略
第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を遺言者の長女〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全部
第3条 遺言者は、前各項に記載した財産以外の遺言者の有する動産その他一切の財産を遺言者の妻〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
特定財産を承継させる遺言の類型として「特定財産を相続させる遺言」を、前回に説明しましたが、続けて説明いたします。
全部相続させる遺言
全部相続させる遺言
- 遺言者の財産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言者が死亡して相続が開始するのと同時に、その遺産の全部が受益相続人に相続により移転することになります。登記実務も財産全部を相続させる旨の遺言により、受益相続人は、遺産に属する不動産全部について、相続による所有権移転の登記を申請することができるとしています。
- 全部相続させる遺言があると、遺産分割の協議や審判の対象となる遺産は、存在しないことになります。判例は、全部相続させる遺言を遺産分割方法の指定と解したうえで、相続分の指定(特定の相続人の相続分を100%とする指定)をともなうものという考え方を採り、相続債務についても特段の事情がない限り、当該相続人にすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであるとしています。
- 全部相続させる遺言については「遺言者の有する一切の財産をAに相続させる」と記載すれば足りますが、相続人に遺産の内容がわかるようにしたり、相続登記や預貯金の払い戻しなどを考えて不動産や預貯金、株式などの有価証券類を具体的に記載しておく例もみられます。
- この遺言にあたっては、遺留分を有する他の相続人は遺留分侵害額請求権の行使として、受益相続人に対し侵害額相当の金銭の支払い請求ができること、相続債務がある場合には、債務もすべて承継することなどに注意する必要があるでしょう。
割合的相続させる遺言
- たとえば「遺産の3分の1をAに、3分の2をBに相続させる」というように、遺産を数人の相続人に一定の割合で相続させる内容の割合的相続させる遺言については、議論があります。
- すなわち、割合的相続させる遺言についても、遺産分割を経ることなく個々の財産に対する各持分割合による権利が各相続人に当然に移転して、物権的な共有ないし準共有関係が生ずる考え方と単なる相続分の指定とみて、改めて遺産分割の手続きにより権利関係の帰属の確定を要するとする考え方があります。
- 公正証書遺言では、相続分の指定については「相続分を次のとおり指定する」あるいは「遺産を次の割合で分割するように定める」の例により、相続分の指定であることを明記するのが一般的です。
- 割合で「相続させる」とした場合でも、当該遺言書の記載から個々の遺産の帰属については、相続人間の協議による旨の遺言者の意思が明らかでない限り、遺産分割を経ることなく当該割合で個々の権利が、物権的に移転する趣旨と解するのが相当であると考えられています。
- その趣旨を明確にするため、不動産について「各2分の1の持分割合による共有として相続させる」などとする例もみられます。
割合的相続させる遺言の文例
次のような書き方が考えられます。
① 遺言者は、遺言者の有する次の土地および建物を、遺言者の妻〇〇〇〇(生年月日)および長男〇〇〇〇(生年月日)に各2分の1の持分割合により相続させる。
(土地・建物の表示)略
② 遺言者は、前項の財産を除く遺言者の有する一切の財産を、いずれも長男〇〇は3分の2、遺言者の次男〇〇〇〇(生年月日)は3分の1の割合により相続させる。
清算型相続させる遺言
清算型相続させる遺言
- 相続させる遺言でも被相続人の積極財産を換価し(不動産の売買、預貯金の払い戻しなど)、相続債務などを弁済、控除したうえで、その残金を相続人に相続させるようにした清算型の遺言をすることができます。
- 財産の全部または不動産の全部はもちろん、たとえば特定の不動産を売却して、その売却費用を控除した残金を分配する旨の遺言をすることもできます。遺産の換価や清算、配分のために、実務では遺言執行者を指定しておくのが通例です。
- 清算型相続させる遺言の対象が不動産の場合、遺言執行者は、当該遺言の執行として、その不動産を売却し、相続人全員への相続登記を経由したうえで、買受人と遺言執行者との共同申請により、買受人への所有権移転登記を行うことになります。
清算型相続させる遺言の遺言文例
第1条 遺言者の有する財産を全部換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に要する費用を控除した残金を、次のとおり相続させます。
妻 〇〇〇〇(生年月日)に4分の3
長男 〇〇〇〇(生年月日)に4分の1
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言にもとづく不動産の売却処分および登記手続きならびに預貯金等の名義変更、解約、払い戻しその他、この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
予備的相続させる遺言(補充遺言)
- 相続させる遺言については、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、または受益相続人が相続放棄をした場合などに備えて、予備的遺言としてあらかじめ当該財産を相続させ、または遺贈するものを定めておくことができます。
- 遺贈については、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない旨の明文の規定があります。
- しかし、相続させる遺言については、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合の効力については、明文の規定はありません。
- 判例は、特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとしました。
- したがって遺言者において、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡したときは、他の者に相続させ、または遺贈したいとの希望を有している場合には、予備的遺言で明示しておくようにします。
予備的相続させる遺言の遺言例
負担付相続させる遺言
- 負担付相続させる遺言とは、遺産を相続させる代わりに受益相続人に一定の負担(法律上の義務)を課する内容の遺言をいいます。
- 負担の内容は経済的なものに限らず、非経済的なもの(妻の看護・世話)でも差し支えありません。単にその履行を期待し、希望する旨を述べたに過ぎないものは負担ではありません。
- 受益相続人は、相続の目的の価額を超えない限度において、当該負担を履行する義務を負います。受益相続人が負担する義務を履行しない場合であっても、当該遺言は当然に無効とはなりません。
- その場合、遺言執行者または他の相続人は、相当の期間を定めて履行を催告することができ、その期間内に履行がないときは、当該遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができるものと考えられます。
負担付遺言の取消し
- 負担付遺言の取消しが認められるのは、その負担が履行されないとすれば、当該遺言をしなかったであろうと考えられる場合に限られます。
- 裁判例として、長男に財産全部を相続させ、その負担として次男の生活を援助するものと定めた負担付相続させる遺言につき、次のように判示しました。
- 少なくとも月額3万円の援助義務を認めたうえで、遺言の文言が抽象的であること、長男は義務の内容が定まれば履行する意思があることなどを考慮すると、長男の責めに帰すことができないやむを得ない事情があり、遺言を取り消すことが遺言者の意思に叶うともいえない、としたものがあります。
- 負担付遺言が取り消されたときは、遡及的に効力を失い、その目的物は相続財産に戻って相続人全員の共有に属することになります。遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思にしたがいます。
負担付相続させる遺言の遺言例
第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。ただし、長男〇〇〇〇は、次の財産を相続することの負担として遺言者の妻〇〇〇〇が死亡するまで、同人と別居し同人を扶養しなければならない。
特定財産承継遺言による権利の承継
特定財産承継遺言による権利の承継
- 特定財産承継遺言があった場合、当該遺言の効力として、特定財産上の権利が、遺産分割など特段の手続きをえることなく、被相続人死亡のときに受益相続人に当然に移転することになります。
- その場合、従前の判例は、相続させる遺言による権利の取得は、法定相続分または指定相続分による相続の場合と、その本質を異にするものではなく、これらの場合と同様、登記なくして第三者に対抗することができるとしていました。
- これに対し平成30年改正法は、その施行日以降に開始した相続に関し、特定財産承継遺言によって特定の不動産に関する権利を相続により承継した受益相続人は、法廷相続分を超える部分については、その旨の登記を備えなければ第三者に対抗することができないとしています。
- たとえば、被相続人の相続人は子A、Bの二人であるところ、被相続人は「甲土地をAに相続させる」旨の遺言をのこしていたものの、「甲土地につき、Aが相続登記をしない間に、BがB単独名義の相続登記をしたうえ、これを第三者Cに譲渡し、Cへの所有権移転の登記を経由した場合、いかに解するべきでしょうか。
- この場合、当該遺言により、甲土地を承継したAは、その法定相続分2分の1を超える部分の取得については、Cに対抗することはできません。
- なお、Aの法定相続分2分の1については、BおよびCはそもそも無権利であるということですから、Aは登記がなくてもCに対抗できます。
被相続人からの譲受人と受益相続人との関係
- 被相続人がその所有する甲土地をAに譲渡したのち、甲土地を相続人Bに相続させる旨の特定財産承継遺言をし、その後に死亡した場合、相続人Bは被相続人がAに対し、譲渡人として負担する登記義務を含め、被相続人の地位を包括承継することになります。
- したがって、AとBは当該譲渡につき、当事者関係に立ちますので、Bが当該遺言にもとづく相続登記をしても、AはBに対し、被相続人からAへの所有権移転を主張することはできます。
- この場合、Bの相続登記を抹消したうえで、改めて被相続人から、Aへの所有権移転の登記を申請するのが本来の形ですが、Bの相続登記を残したまま、直接BからAへの所有権移転の登記を申請することもできます。
- ちなみに、被相続人が甲土地をAに譲渡したのち、相続人Bを受遺者として甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合には、AとBは対抗関係に立ち(被相続人による二重譲渡の場合と同じ)、相続開始後、先にBが当該遺言にもとづく遺贈による所有権移転の登記をしたときは、Bは、その所有権の取得をAに対抗することができます。
受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡の場合
判例の考え方
- 従前、相続させる遺言により遺産を相続させるとさせた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、当該遺言は、当然に執行して、その代襲者に効力が及ぶことはないと考えるのか、あるいは相続の法理にしたがい、代襲相続を認めるのが相当であると考えるのか、という点については、議論がありました。
- この点が争われたのが最高裁平成23年2月22日判決です。
事案は、Aが相続財産を子Bに相続させる旨の条項および遺言執行者の指定にかかる条項の二箇条からなる公正証書遺言を作成していました。Aの死亡前にBが死亡したことから、Aのもう一人の子XがBの子であるYらに対し、Aの遺産である土地建物について、持分2分の1を有することの確認を求めたものです。
- 判決は、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割方法を指定する遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解されます。
- 当該遺言により、遺産を相続させるとさせた推定相続人が、遺言者の死亡以前に死亡した場合は、遺言者が当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力が生ずることはないと解するのが相当であります。
- 本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項および遺言執行者指定に係る条項の二箇条しかありません。Aの死亡以前に死亡したBが承継すべきだった財産を、B以外の者に承継させる意思を推知させる条項はないから、上記特段の事情があるとはいえず、本件遺言はその効力を生ずることはないとしました。
相続債務との関係
- 被相続人の債務は、一身専属的な債務でない限り、各相続人の相続分に応じて承継されます。
- 共同相続人のうちの一人に財産全部を相続させる旨の遺言があった場合における相続債務の承継につき、判例は次のように述べています。
- 当該遺言により、相続分の全部が当該相続人に指定された場合には、特段の事情がない限り、当該相続人に相続債務をすべて相続させる旨の意思が表示されたものとして、相続人間では、当該相続人が相続債務をすべて承継することになります。
- しかし、相続債権者に対しては、その効力がおよばず各相続人は相続債権者から法定相続分による相続債務の履行を求められたときは、これに応じなければなりません。
- 他方、相続債権者から相続分指定の効力を承認し、当該相続人に対し、その全部の履行を請求することは、妨げられないとしています。
- 平成30年民法改正では、相続債務の債権者は、① 各相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができ、また、② 共同相続人の一人に対して、指定相続分に応じた債務の承継を承認して、指定相続分に応じてその権利を行使することもできるとして、これを明文化しています。
- 法定相続分を下回る相続分の指定がされた相続人が、法定相続分に応じた債務の支払いをしたときは、これを上回る指定を受けた相続人に対し、求償権を行使することができます。
特定財産承継遺言と特別受益
- 特定財産承継遺言があった場合、当該特定財産は特段の事情がない限り、受益相続人が被相続人死亡のときに、ただちに相続によりその権利を取得することになります。
- その場合、遺贈であれば、特別受益として取り扱われますが、特定財産承継遺言による遺産の承継については、明文がありませんので、その一人が問題になります。
- この問題については、民法903条を類推適用して特定遺産を遺贈財産と同様に特別受益として扱うのを相当とする考え方があります。
- また、特定財産承継遺言は遺産分割方法の指定であって、特定遺産は一部分割されたものと解し、場合によっては代償義務を課し、全体的に遺産分割を行うべきとする考え方があります。
- 前者であれば、特定遺産が具体的相続分を超える場合でも、超過額について代償金を支払う必要はないのに対し、後者であれば、超過部分について代償金の支払いが問題となります。
- 裁判例として、相続させる遺言による特定遺産の承継についても、民法903条1項の類推適用により、特別受益として持戻し計算の対象となるとしたものがあります。
- また、他の裁判例として、特定物を相続させる遺言により、当該特定物は、被相続人の死亡と同時に、当該相続人に移転し、現実の遺産分割は、残された遺産についてのみ、行われるのであるから、特定遺贈があって、残された遺産について遺産分割が行われる場合と類似しているとして、民法903条1項の類推適用により特別受益の持戻しと同様の処理をするべきであるとしたものがあります。
特定財産承継遺言による利益放棄の可否
- 特定財産承継遺言によって特定の遺産を相続することとなった受益相続人が、その特定の遺産の取得を希望しない場合、これを放棄することができるか否かについては議論があります。
- すなわち、遺言によって財産全部を相続させる、または包括遺贈するとされている場合、受益相続人または包括受遺者がその承継を望まず、これを放棄したいと考える場合には家庭裁判所に対し、相続の放棄または包括遺贈の放棄を申述をすることができます。
- また、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでもこれを放棄することができます。
- ところが、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の特定相続承継遺言は、遺産分割方法の指定として位置付けられ、その放棄(遺言の利益の放棄)に関する規定はありません。
- もちろん受益相続人が相続放棄をすること自体は差し支えありませんが、相続放棄をすれば相続人の地位を喪失し、当該特定遺産はもとより、その余りの遺産を取得することもなく、共同相続人間の遺産分割の協議に加わる資格も失います。
- 問題は、特定遺贈の放棄と同様に、特定財産承継遺言による特定の遺産の取得の利益のみを放棄することができるかという点です。
- これが可能とすれば、当該特定遺産は他の遺産とともに遺産分割の対象となり、あらためて受益相続人を含む相続人全員の協議または家庭裁判所の審判・調停により、遺産分割が行われることになります。
- この点については、2つの考えがあります。
① 遺産分割方法の指定および相続分の指定については、承認・放棄の制度はなく、遺贈のような明文の規定を欠くこと、あるいは相続人は遺言者の意思に拘束され、相続人の一人が無条件かつ一方的に変更することはできないとして、これを消極に解する考え方(利益放棄否定説)があります。
② 被相続人の意思であっても受益相続人の意思をまったく無視して拘束することはできないこと、受益相続人に対してまったく遺産の取得ができなくなる相続放棄か、希望しない特定遺産の取得かの二者択一を迫るのは不当であることなどから、特定遺贈の放棄に関する民法986条1項の趣旨は、相続させる遺言(特定財産承継遺言)にも妥当するとして、これを積極に解する考え方(利益放棄肯定説)があります。
特定財産承継遺言による相続登記
- 財産の全部または不動産の全部もしくは特定の不動産を、特定の相続人に相続させる旨の特定財産承継遺言があった場合、当該相続人は被相続人の死亡と同時に当該不動産上の権利を相続により承継することになりますので、当該不動産につき、単独で「相続」を登記原因とする所有権移転の登記を申請することができます。
- 「特定財産承継遺言による相続」を登記原因とする所有権移転の登記の申請にあたっては、登記原因証明情報として当該遺言書のほか被相続人が死亡して相続が開始した事実および申請人が相続人であることを証する戸籍事項証明書を提供すれば足り、相続人全員の戸籍・除籍事項証明書などの提供を要しません。
- 遺言書(遺言公正証書および法務局保管の遺言書を除く)は、家庭裁判所の検認を経たものであることを要します。法務局保管の遺言書については、遺言書情報証明書を提供します。
法定相続分での相続登記がされている場合
- 従前の登記実務では、たとえば共同相続人甲、乙のうち、甲に特定の不動産を相続させる旨の特定財産承継遺言があったが、甲が当該遺言による相続登記をする前に乙が法定相続分による甲および乙への相続登記を経由した場合については、次のように解していました。
- これを甲単独名義とするには、所有権の更生の登記の方法により、かつ甲を登記権利者、乙を登記義務者とする共同申請によるべきものとされていました。
- しかし今般、登記権利者となる甲が単独で所有権の更生の登記を申請することはできることとされました。
- この場合の登記原因およびその日付は「年月日特定財産承継遺言」とし、登記原因証明情報として遺言書の提供を要します。また、当該更生登記につき登記上の利害関係人があるときは、その承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本の提供を要します。
従前の遺言執行者の登記申請権限
- 従前の登記実務では、相続させる遺言により特定の不動産を相続することとなった場合には、遺言執行者に相続登記を申請する代理権限はなく、当該相続人から申請すべきであるとの取り扱いがされてきました。
- また、判例は相続させる遺言により受益相続人が特定の不動産の所有権を相続した場合、当該相続人は単独でその旨の所有権移転登記手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として当該登記手続きをする義務を追うものではないとし、当該不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者は登記手続きをすべき権利も義務も有しないとしてきました。
平成30年改正法における遺言執行者の登記申請権限
- 判例の立場は、受益相続人に当該不動産の所有権移転登記を取得させることは、遺言執行者の本来的な職務権限に含まれるが、登記手続き上、被相続人名義である限り受益相続人による単独申請ができる以上、遺言執行者の職務は顕在化しないものと理解されていました。
- 平成30年改正では、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することはできないとされたことなどから、特定財産承継遺言があったときは、被相続人が遺言で別段の意思を表示しない限り、遺言執行者は、受益の相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることはできることとしています。
- したがって、当該遺言が平成30年改正法の施行以後にされた特定財産承継遺言である場合には、遺言執行者は単独で相続による所有権移転の登記を申請することができます。なお、従前と同様、受益相続人自らが特定財産承継遺言にもとづいて相続による所有権移転の登記を申請することは差し支えありません。
お問い合わせ・ご相談

せんげん台駅 西口 1分
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所の5つの安心
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!
「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
お問い合わせ・ご相談

せんげん台駅 西口 1分
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

越谷 司法書士・行政書士事務所
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
お問い合わせ
代表司法書士

美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
オリジナル 解説

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
新着情報
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。